- 要件事実論30講/村田 渉

- ¥3,990
- Amazon.co.jp
今修習をしている方から、すすめられました。
合否がわからな今の段階でおすすめの勉強を聞いたところ、修習にむけた準備をすれば
合格→あわてないですむ、不合格→来年の受験に役立つ、とのこと。
今年の択一民訴、論文民法でもがっつり要件事実を聞いてきてましたしね。
1回ゼミでやったのですが、もう1回やる価値がありそうですね。

今修習をしている方から、すすめられました。
合否がわからな今の段階でおすすめの勉強を聞いたところ、修習にむけた準備をすれば
合格→あわてないですむ、不合格→来年の受験に役立つ、とのこと。
今年の択一民訴、論文民法でもがっつり要件事実を聞いてきてましたしね。
1回ゼミでやったのですが、もう1回やる価値がありそうですね。
先週読んだ本です。
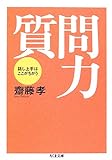
上手なコミュニケーションは上手な質問からはじまるということを著名人の会話例を挙げながら説明しています。
確かに、私の自身の周りでもコミュニケーションが上手な人は、質問が上手い。
ただ、上手な質問ってなかなか難しいところですよね。考えすぎると会話のテンポがとまってしまうし、つまらない質問は会話を終わらせてしまいますし。
この本を読んだからといって、すぐに質問力があがるというわけではありませんが、上手な質問のイメージはつかめると思います。分量も多くなく、さらっと読めます。
ふと部屋を見渡すと、
部屋がとても汚いではないか・・・。
よし掃除しようと思った、が、根が適当な私はただ掃除するだけでは
部屋の隅々まで掃除しない違いない。
大晦日でもないので、大掃除だ!という気分にもなれない。
そこで、いっそのこと模様替えしようということになった(自分のなかで)。
まずは、部屋の間取りを書いて、どこに何を置くかを考える。以前、何も考えないで家具を動かしてしまったら
身動きがとれなくなって大変なことになった。そのとき得た教訓である。
ん??家具の置き場所を考えていたらもう夕方ではないか。
こうして、模様替えという名の大掃除は明日以降へと延期されることとなった。
先日お会いしたローの実務家教員に、試験が終わったあと発表までの間の過ごし方について
アドバイスを頂きました。
1つは、昨日も書いたように簿記の勉強を勧められました。
もう1つ勧められたのが、民事執行・保全法の勉強です。
確かに考えてみると実務では重要にもかかわらず新司の受験という観点からは手薄になりがちな分野です。
ついでにお勧めの本を教えていただきました。

簿記の勉強に平行して、読んでみたいと思います。
試験後目標がないとだらだらと過ごしてしまいそうだったので
簿記3級をうけることにしていた。
以前から、簿記の勉強もしておかなければと思っていたのだが
なかなか時間がとれずに放置していた。
やってみるとなかなか面白い。特に手形については、どのように
使われるのか具体的なイメージがつかめる。
今度の6月の3級の試験に合格できたら、11月に2級をうけてみようと思う。
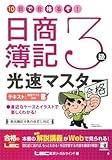
今読んでいる本です。

タイムリーに、今日北朝鮮で核実験が行われたもようとの報道があった。
その報道をどこか他人事のようにみてしまっている自分がこの本に描かれている日本人とおどろくほど合致していてすこし気持ち悪くなった。
事例から刑法を考える (法学教室Library)/島田 聡一郎

刑法の演習書として主に使用していました。
これは、去年合格した先輩に進められたもので
法学教室で連載されていた「事例で学ぶ刑法」
を書籍化したものです。
教科書にはあまり詳しく書いてないけれども学会では
ホットな話題をネタに問題を作成しているようです。
骨のある問題が多いので一人で潰すには根気がいるかも。
友人とゼミを組んで潰すとよいのではないでしょうか。
私が答案作成する際に使用しているペンはこちら、

万年筆といってもお手ごろな価格で臆せず使えます。
ペン先のサイズはEF(極細)を利用していました。
EF(極細)といっても結構太く、日本製のボールペンでいう
0.5くらいの太さはあると思います。
コンバーターを一緒に利用すれば、カートリッジよりインク代
を節約できます。

平成21年5月21日から裁判員制度が始まります。
連日報道されていますね。
報道番組等でなされている街頭インタビューをみると、裁判員制度に戸惑いを覚えている方が多いという印象を受けます(あくまでも報道されている範囲で)。
裁判員制度に消極的な方の意見は次のようなものです。
①素人の自分が判断できるはずがない(自信がない)
②仕事を休まなければならないのが困る
③被告人に不利な判断をした際に復讐されるのではないかという不安がある。
このうちの①の意見については
まさしく法律の専門家でない方の様々な意見を取り入れることがこの制度のねらいです。様々な経験を持っている方々の様々な視点をいかしより妥当な「事実認定」「量刑判断」をしようという狙いです。ですから、裁判員に選ばれた方は自分が専門家ではないことを不安に思う必要がないように思います。
また、判断の場には裁判官も加わり専門的知識についてのアドバイスをしたり、判断の手助けになるような資料の提供も行われるようです。
次に②についてですが、
法令にはには裁判員を辞退できる場合が定められています。
そのなかに、「事業上の重要な用務を自分で処理しないと著しい損害が生じるおそれがある」場合には辞退が認められるようです。
もっとも、「著しい損害」かどうかの判断はケースバイケースなので、上記の定めがあっても、②の不安は簡単には解消されないでしょうね。
*その他の辞退理由も法務省の法務ページに説明があります。
そして、③についてですが、法務省は、
①これまで裁判官や裁判所職員が事件関係者から危害を加えられたというような事件はほとんどおきていない,②事件関係者から危害を加えられるおそれのある例外的な事件については,裁判官のみで審理することになっている
③裁判員の名前や住所は公にされないことになっていますが,万一にも事件関係者に知られることがないように,裁判員の個人情報については厳重に管理する
等の説明をしています。
もし興味・疑問があるならば、ぜひ一度法務省のホームページをみることをお勧めします。
法務省裁判員制度について(http://www.saibanin.courts.go.jp/index.html )
最近手に入れた便利グッズを紹介します。
これは何でしょうか?
実は
これを開くと
そう、付箋ケースなんです。
付箋って筆箱に入れてるとすぐに、ばらばらになったり、消しゴムのくずがついて汚れたりしますよね。
私は勉強の際によく付箋を使うのですが、この付箋達どうにかならないのかなーと、いつも思っていました。
と、先日ロフトの革小物売り場で発見!値段は1000円弱だったので、こいつ小さいくせにちょっと高い、と思いながらも購入。文房具好きな私は、誘惑に勝てなかった。
この付箋ケース、どんな構造かというと、開閉するところが磁石で、あけるとセンターのところ(上の写真でいうと付箋が張ってあるところ)にプラスティックの板が張ってあって、付箋をペタッと張れるようになっています。
筆箱の中に入れていても、付箋がばらばらにならず、ごみで汚れることもありません。
私は買ってよかったと思っています。
私のように、この付箋達どうにかならないかなー、と思っている方にはおすすめです。